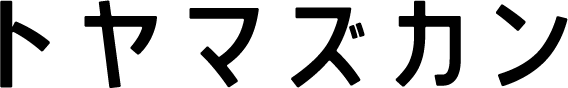溢れるバイタリティー 南アフリカワインの伝道師となった経緯に迫る
ミラー香保里さん Humming bird ワインインポーター
富山の老舗呉服問屋「牛島屋」に生まれ、ロンドン留学を経てファッション誌編集者となり、今では南アフリカワインの輸入販売事業を手掛けるミラー香保里さん。南アフリカ人の夫と結婚し、2児の母として子育てと仕事を両立。バイタリティーに富んだ経験を生かし、南アフリカと日本の架け橋となるべく活躍する女性の開拓者に富山で働く意義や将来の展望を聞いた。

「私がインポーターの免許取って、直接売った方がよい」
Q 南アフリカワインを取り扱うきっかけとなったのは?
2015年に南アフリカ人の主人のいとこがワインの醸造家と結婚して、そうした縁もあって、その醸造家が作った南アフリカワインを飲んでみると本当においしかった。日本にもほとんど入ってきていないワインで、これを売れないかと考えたのが始まりですね。
それで、色々な知人を介して、三越伊勢丹ホールディングスの当時の社長だった大西洋さんに直接お会いする機会があって。そこで販売に向けたプレゼンをしたら気に入ってくださって、南アフリカワインを伊勢丹で売りたいという話になった。
ただ、当初、私はどこかのワインのインポーター(輸入業者)と伊勢丹をつなげればいいのかと軽く考えていたんです。そしたら、インポーターは直接ワインを買い付けて販売するわけですから、間に入ることで利益は減るんですよね。そうしたことも踏まえて、いろいろと考えた結果、私がインポーターの免許を取得して、直接やりとりした方がよいと思ったんです。翌年4月に免許を取得し、同じくらいの時期に富山と石川、あと東京の伊勢丹新宿店で南アフリカワインの販売が始まりました。
Q 販売は順調でしたか?
伊勢丹新宿店が取り扱うのはフランスとイタリアのワインがメインで、その中で南アフリカワインは8種類くらいしか置いていなかったんです。お客さんは買いに来る銘柄がほぼ決まっていて、弊社で輸入してきた新しい南アフリカワインを置いていただくまで少し時間がかかりました。1種類でしたが、売る場所を空けてくださいました。上顧客様向けの展示会「丹青会」でもご紹介いただき、とても嬉しかったですね。
そこからは本当にがむしゃらに向き合って、インポーターとしての事業を本格化させました。翌年には取り扱う南アフリカワインは20種類くらいに増え、その後も南アフリカの醸造家からのアプローチもあり種類を増やしていきました。
もともと私は酒屋でもなく、お酒に関わるバックグラウンドもない中、自分の感覚だけを背負ってワインを扱う仕事を始めたわけです。お酒を扱う仕事、日本では男社会のイメージが強く、最初は気難しいおじさんたちからは「小娘が何しに来た」みたいな感じで扱われましたよ。
でも、一旦打ち解けると、そうした方々はすごくかわいがってくださる。まだまだひよっこのハミングバードを応援してくださり、本当に皆さんに支えてもらってここまで来られました。お客様にワインの魅力を伝えることで南アフリカ自体にも興味を持ってくださったり、南アフリカワインに対する感じ方や飲み方も変わってきたなと感じています。
Q 新型コロナウイルスの感染拡大で、お酒を飲んだり海外に行く機会が激減した影響はありますか?
お店で待つというよりも、南アフリカワインに興味を持つお客様に会いに行ったり、イベントに出店して飲みながらコミュニケーションを取るのが私たちの販売スタイル。ワインは自社のウェブストアで売ることもできますし、やはりダイレクトにお客さんにつながるのが、南アフリカワインの魅力を伝える上で一番大切だと思います。
コロナ禍では、(ビデオ会議システムの)Zoomを使い、南アフリカの醸造家とお客さんをつないで南アフリカワインをテイスティングするというイベントを企画しました。コロナ禍で南アフリカに行きにくい今だからこそ、現地の醸造家とつながれることがお客さんにとっては〝非日常〟なんですね。そもそも、現地の醸造家と話す機会も珍しかっただけに、ものすごくお客さんから喜んでもらえました。
私の中ではワインっていうのは〝コミュニケーションツール〟であって、私たちは醸造家の〝メッセンジャー〟でもあるので、その思いが届くようにとにかく丁寧に取り扱うようにしています。数ある中から何故、南アフリカワインを皆さんが手に取ってくれるのか、そして長く愛してもらうためにはどうしたらいいのかを常に考えています。
Q 富山での南アフリカワインの反応は?
北陸3県の中では、富山は国やタイプを問わず、さまざまなワインを愉しまれる人が多い印象です。富山は色々なことに興味や好奇心を持って、南アフリカワインについても「じゃあ、買ってみようか」と言ってくださる人が多いように感じます。
実は富山を拠点にしているワインインポーターは私たちだけではありません。氷見でオーストラリア・ニュージーランドのワインを扱う「ヴィレッジ・セラーズ」さんは、オーストラリア出身のコーエン夫妻が1980年代に輸入卸を始めたパイオニア的存在です。モルドバ人とロシア人が営むモルドバワインを扱う会社もあり、多様性があるんです。そういう意味では、富山は色々な可能性がある場所だと思いますね。世界に通ずるものを作ってますよ。富山には世界に誇る食と美があるのだと、ワインの仕事を始めてから気づきました。
Q 特に影響を受けた人はいますか?
枡田酒造店の(5代目社長の)桝田隆一郎さんのラグジュアリーに対する哲学に影響を受けました。東岩瀬の街再生はもちろん、シャープな審美眼を持ち、全身全霊で日本酒文化を世界へ発信される姿には学ぶことがとても多いです。また、南砺市のワイナリー「ドメーヌ・ボー」を運営するトレボー株式会社代表取締役の中山安治さんには『情熱は伝播する』ことを教えていただきました。私がワインビジネスをスタートするに当たり、お二人に本当に支えていただいたので。お酒という仕事を通じて、人を集めて場所を作り出せることはすごいことだと思います。

「『ポーカーフェースの武内』と呼ばれるようになった(笑)」
Q ちなみに、南アフリカ人のご主人と結婚に至ったきっかけは?
大学卒業後にロンドンに留学してファッションプロモーションを専門に学んでいたのですけど、アルバイト先のコーヒーショップで主人と出会いました。彼は私の上司で、ワーキングホリデーでロンドンに来ていて、身長も私より40センチくらい高かった。見上げるように話していたのですけど、話してみると意外に奥ゆかしくて(笑)。
当時、私は南アフリカのことをまったく知らなくて、人種隔離政策のアパルトヘイトが行われれば、白人もいるし、歴史的にも色々なことがあった国なんだなと改めて認識するようになりました。彼と話していると、南アフリカ人は日本人以上に周りの〝人〟のことを考え、謙虚さを持ち合わせていると感じましたね。それで、話をしているうちに意気投合して、付き合い始めたのですが、彼は都会が好きじゃなかったので、ワーキングホリデーが終わったらすぐに帰国して地元の大学に通い始めたんですよ。
私はファッションエディターの仕事がしたくてロンドンに残ろうと思ったのですけど、両親から「このままずっとロンドンにいるなら勘当する。もし、残りたいなら全て自力で何とかしなさい」と言われて…。親の助けも受けていたので、悩みながらも日本に戻ることを決めました。その後も、彼とは遠距離恋愛を続けていました。
Q 日本に戻ってからはどのような生活を送られたのですか?
ファッション誌の編集部で仕事をしたかったのですけど、すぐには就けなかったですね。そこで仕事を探す中で紹介頂いた東京・広尾にあるPRコンサルタント会社のWAGで働くことになりました。
社長の伊藤美恵さんは元デザイナーで、日本における「アタッシェ・ドゥ・プレス(広報・PR)」の先駆者的存在。ファッション業界でも影響力が大きく、まるで日本版アナ・ウィンター(米版『VOGUE』の伝説の編集長)のようなパワフルな女性でした。面接に行ったときには「あなた編集やりたいの?私がさせてあげるわよ」と言ってくれるようなたくましい人でしたね。
そんな会社に拾っていただいて働くことになりました。私は3~4年日本を離れて、当時は生意気だったと思います。最初はアシスタントとして広告代理店などの会議に一緒に行くのですけど、複数の案件を持たされてよく分からず、自信がなさそうにしていると「PRの仕事をしているときに、焦っている姿を見せてはダメ。常にポーカーフェイスよ」と言われて、分かっていなくても分かっているように振舞うように指導されました。不安な顔を見せるとクライアントが心配するから、と。また、ファッションショーやイベントの現場にいると、ハプニングは付き物。平常心でいることの大切さは、その後の人生でものすごく役に立っていますね。
Q 仕事は充実していたようですね
忙しかったですね。本当に寝る時間がなくて、深夜3時まで仕事して、お風呂と着替えに家に帰り、また午前9時に会社に行くみたいな。そんな生活が2年半続きました。仕事に邁進するしかないので、ある意味ありがたかったのですけど…。
その後、憧れていたファッションエディターの方に誘って頂き、念願の編集者の仕事に就けました。アメリカのファッション雑誌「Harper’s BAZAAR」日本版のファッション担当だったのですが、またドロドロの生活。3日徹夜とか当たり前のような生活でしたけど、自分の作りたいページを自分で采配し、自分が企画を作り、それが本になったときの気持ちは何とも言えない充実感がありましたね。3号くらい先の編集も同時進行で常に動いていないといけない職場でした。
Q 結婚はどのタイミングでされたのですか?
雑誌の編集者に転職して半年が過ぎた頃、彼も大学を卒業して、日本に来て英語の教師として働き始めました。先輩からは「結婚は先延ばししたらダメ」という助言もいただき、娘の誕生も後押しして、このタイミングで結婚しましたね。いわゆる今でいう「授かり婚」(笑)。娘が生後7カ月のときに明治神宮で結婚式を挙げました。
長女を授かってからは産休も取りましたけど、育休が終わって娘を保育園に預けてから仕事復帰すると、お迎えの最終時間にタクシーで駆け込む日々。でも、その2年後に長男を授かったときに、2人育てながらこの仕事はさすがに厳しいなと思い始めました。
Q それが富山に戻るきっかけになったんですね?
5年間編集の仕事に携わり、ある程度、自分では達成感もあった。当時はリーマン・ショックで広告ありきのファッション誌の存続の危機を迎えていたし、一線を引こうかなと。ある意味で良い時期に退いたとは思っています。主人も田舎が好きで、英語教師の仕事は富山でもできるということで、富山に戻ることになりました。東日本大震災の少し前の2011年です。

「富山に『行きたい!』思わせるような情報発信が私の仕事」
Q 富山でも有名な老舗呉服店の生まれで、そうした老舗の看板を背負っていることのプレッシャーのようなものを感じましたか?
幸い、実家の呉服屋は代々長男が跡継ぎと決まっていたので、プレッシャーはまったくありませんでした。イギリス留学、ファッションPR、雑誌編集者としての経験が、今の仕事にも大いに役立っていると思います。生まれ育った富山で人と人を繋ぎ、南アフリカと日本の懸け橋になれるような仕事を続けていきたいと思います。
Q 富山には25~39歳の女性が戻ってこない率がワースト2位といわれています。なぜ戻ってこないのでしょうか?
わからないのですけど、五輪で活躍した20代の選手は海外に出たりしてますよね。インターネットやSNSで世界が近くなり、絶対に富山にいたいという理由が若い世代には見つからないのかもしれませんね。私も富山の真の魅力に気づいたのは11年前に帰省してからですから(笑)
Q 国内外が一目置くようなものを富山で創らないといけない?
久しぶりに富山に戻って来たら、幼少期には栄えていたこの商店街もシャッター商店街になっているし、やはり魅力がなかったのかもしれない。「もう富山、終わっている」みたいな感じになって悲しかったですよね。でも、それはどこの地方も同じだと思います。
コロナ禍を経て、人々は「ていねいな暮らし」を楽むようになり、若い世代がクオリティーに価値を見いだしています。富山にはすでに世界に誇る食と美があるので、上手に情報発信してつなげていければよいと思います。やはり、実際に来てもらわないと伝えきれない。南アフリカも富山もそう。「行きたい!」と思わせるような情報発信をすることが私の仕事だと思います。
Q 富山に苦言を呈すならば?
富山はスピード感がない。例えば、(米プロバスケットボールNBAの)八村塁(富山市出身)があれだけ活躍していて、富山から世界へ発信できるビジネスチャンスがたくさんあるのに、スピード感を持ってアピールできていないのはとても残念。
だけど、守りに入ってばかりでは変化は生まれない。このままでは若者は富山に帰ってこないと思う。もっと若い人が活躍できる場が増え、スピード感を持って引っ張っていけるような環境になれば良いですね。
Q 今後の夢は?
南アフリカで日本の素晴らしさを伝えたい。それはワイン事業を始めたころから抱いていた目標です。まずは、南アフリカのワイナリーに世界のVIPが集う、オーセンティックな割烹を作ること。そして、富山の素晴らしい料理人の方々にゲストシェフとしてお迎えできるように、夢に向かって頑張ります!