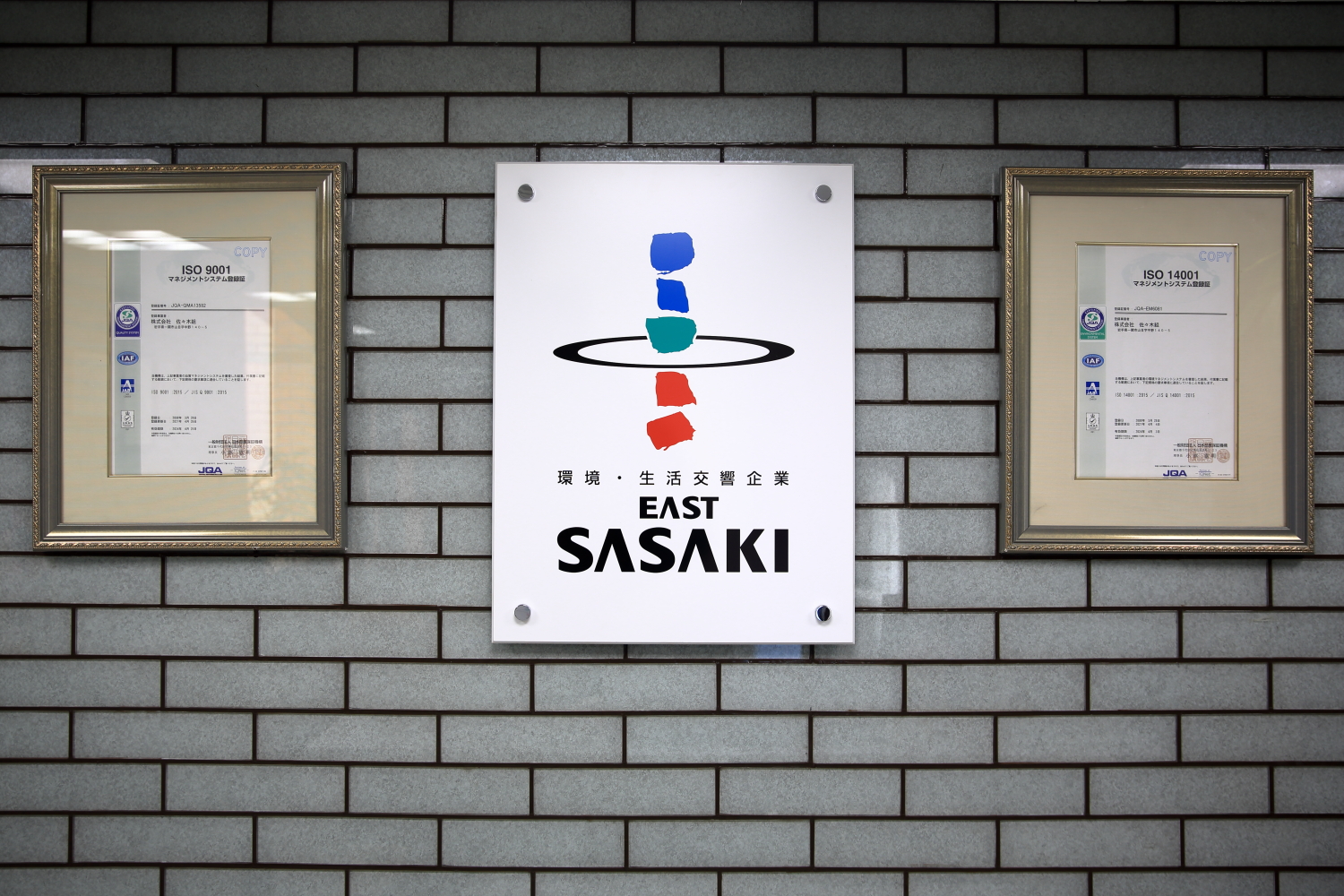LIFE
今、自分らしい働き方と暮らしを見つけよう。
イワイズカンは、
宮城県北・岩手県南エリアの
仕事と暮らしを伝える求人メディアです。
これからどこで、どう生きていくのかを迷った時、
そこに住む人の生き方・働き方・暮らし方が
次の道しるべになることがあります。
まずはイワイズカンを開くところから。
更新日 : 2025年08月22日
更新日 : 2025年07月10日
更新日 : 2025年05月02日
更新日 : 2023年12月11日
更新日 : 2023年11月30日
更新日 : 2023年11月28日
更新日 : 2023年11月22日
更新日 : 2023年10月15日
更新日 : 2023年10月09日
更新日 : 2023年10月09日
更新日 : 2023年07月19日
更新日 : 2023年07月19日
更新日 : 2023年06月02日
更新日 : 2023年06月02日
更新日 : 2023年05月01日
更新日 : 2023年04月14日
更新日 : 2023年04月03日
更新日 : 2023年03月27日
更新日 : 2023年03月27日
更新日 : 2023年03月13日
更新日 : 2023年03月01日
更新日 : 2023年02月18日
更新日 : 2023年02月16日
更新日 : 2023年02月14日
更新日 : 2023年02月06日
更新日 : 2023年02月01日
更新日 : 2023年01月31日
更新日 : 2023年01月25日
更新日 : 2023年01月23日
更新日 : 2022年12月28日
更新日 : 2022年12月28日
更新日 : 2022年12月02日
更新日 : 2022年12月01日